専門委員会委員長・ワーキンググループ座長挨拶
専門委員会の任務
- 専門委員会は、それぞれの分担事項について会議の諮問に対し答申を行うものとする。
- 専門委員会の委員長は、総会及び理事会に出席して担当事項について報告し、意見を述べることができる。
- 専門委員会の委員長は、各専門委員会相互の横断的連携、自主性、整合性を図るために委員長会を置くことができる。
- 委員長会は、委員長を互選により選び委員長は会議の内容と結果を総会及び理事会に出席して報告し、意見を述べることができる。
医学教育委員会 委員長

大学医学部入学試験制度検討小委員会 委員長

2022年度より当小委員会の委員長を拝命しております東田修二と申します。当小委員会は、公正な医学部入試のあるべき姿としての規範を整備し、その遵守状況をモニターすることを目的として、2018年に設置されました。これまでの委員長と委員の先生方のご尽力により、入試の公正さを検証し、その役割が遂行されて参りました。
一方、医学部入試は、公正さだけではなく、学力のみに偏らずに、思考力や協調性をも評価できる選抜方法が求められます。また、多様な人材を選抜するため、一般入試に加えて、推薦入試、学士編入学入試、帰国生入試など多様な入試区分が設けられています。こうした入試の多様性について、全国医学部の入試のアンケート調査を行い、その実態と課題についての報告書をまとめ、2024年3月に全国の医学部に送付しました。
当小委員会はこうした課題に向き合い、さらに良い入試制度を目指して引き続き活動して参りますので、皆様のご指導とご協力をお願い申し上げます。
国家試験改善検討ワーキンググループ 座長

医師国家試験は、卒前教育・卒後臨床研修などの一連の医師養成過程の中に位置付けられており、医学部のカリキュラムに大きな影響を与えています。医道審議会医師分科会の方針に従い、CBT、OSCEは共用試験として公的化が進みました。本来は、この変化に対応して医師国家試験も改革が進むことになっています。しかし、実際には国家試験は前例踏襲の旧態依然とした体制であり、大きな変化がありません。医学生が各段階で適正な評価を受けることはよいことですが、現状はいわゆる「評価疲れ」の状態となり医学生の大きな負担となっています。
モデル・コア・カリキュラムが整備され、JACMEの認証により、各大学医学部の教育体制の標準化が進んでいます。医学知識はCBT、臨床技能・態度はPre-CC
とPost-CCのOSCEで公的な評価を受けるようになった今日、医師国家試験に求められる役割は大きく変化しているのではないでしょうか。
本WGは、毎年、学生、教員を対象として「医師国家試験に関するアンケート調査」を独自に行い、この結果に基づいて厚生労働省など関係機関に要望書を提出し、医師国家試験の改善に向けて活動してきました。今後も、アンケート結果を基に、医師国家試験の現状と今後のあり方について検証を重ね、実質的な医師国家試験の改善に結びつくように要望をまとめるだけでなく、関係省庁と現実的なディスカッションを行っていきたいと考えています。みなさまにもぜひ建設的な意見をお寄せいただきますよう、よろしくお願い申し上げます。
卒後臨床研修検討ワーキンググループ 座長

医学教育委員会の下で、卒後臨床研修の今後の在り方を検討するワーキンググループです。2004年に導入された臨床研修制度により、医師の地域偏在と診療科偏在、基礎医学研究者の激減、医師としてのプロフェッショナリズムの低下などが問題になっています。医師の地域偏在を解消するため都道府県別のシーリングが設定され、2022年度の改訂では、基礎研究医プログラムや地域医療重点プログラムが設けられていますが、これらの実効性に関して検証が必要でしょう。大学病院の研修医獲得状況は悪化傾向にあり、ここ数年のマッチング率も40%を切っています。大学病院の研修医獲得状況を改善する方策を検討する必要があります。2022年度に実施した医師臨床研修制度に関するアンケート調査結果から明らかとなった卒後臨床研修の問題点と今後の在り方について抜本的な改革案の検討が求められています。さらに、2024年4月から開始された医師の働き方改革が、卒前・卒後から専門医養成までのシームレスな教育体制構築に与える影響を検討し、対策案を議論していきたいと考えておりますので、よろしくお願い申し上げます。
専門医に関するワーキンググループ 座長

(掲載準備中)
共用試験検討委員会 委員長
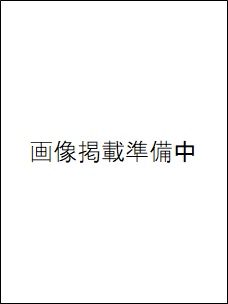
(掲載準備中)
研究・医学部大学院のあり方検討委員会 委員長

医学部大学院はこれまで我が国の生命医科学研究のドライビングフォースとして大きな役割を果たすとともに、physician scientistと呼ばれる多様・多彩で優秀な人材を輩出してきました。しかし、平成16年に導入された初期研修医制度、昨今の新専門医制度の導入により、医学部卒業生は卒後も長期の臨床研修を強いられ、医学部卒業生が研究を開始する年齢の高齢化、また研究を志向する者の激減を招くことになっています。しかも、(これは良い面でもありますが)学部教育自体が国際認証やコアカリの導入もあり、より臨床実習を含めて充実してきています。例えるなら、A教習所を終えたあと、路上にでることなく、さらにB教習所での教習所内での実習を課されるということになります(教習所内の期間を延ばすことが運転技術の向上に繋がることなどありえません。)。この問題に対する対策として、限られた定員・施設での研究医制度も導入され、それはそれで大変意義のあることですが、新しい研究領域の創出、優秀な研究者の育成は、広いすそ野と地盤があってこそですし、そのような土壌こそが国の品格とも感じます。本委員会では、これらの課題を検討し、医学研究及び医学部大学院のあり方を議論して提言していきたいと考えております。
動物実験検討委員会 委員長

令和4年度より、動物実験検討委員会委員長を務めております名古屋大学の木村 宏と申します。当委員会では引き続き、「動物の愛護及び管理に関する法律」に基づいて、様々な角度から我が国の動物実験の在り方について議論を深める予定です。代替手段のない場合、動物実験は医学研究に極めて重要なものであり、今後も、人類の福祉に大きく貢献することが期待されます。一方、我々は、今後とも動物実験の3Rの原則に基づいて、動物愛護の観点からも一層の厳格な運用に努めなければなりません。これからも、動物愛護の精神を尊んだ、透明性の高い動物実験の運営にご協力をお願いいたします。
地域の医療及び医師養成の在り方に関する委員会 委員長

(掲載準備中)
患者安全推進委員会 委員長

この度、「患者安全推進委員会」の委員長を拝命させて頂きました日本大学医学部の木下浩作です。どうぞよろしくお願い申し上げます。
本委員会は、「医療に対する安全・安心をより向上させる」という意味を込め「患者安全推進委員会」と改称され、これまでも活発な議論が行われてきました。最近の主な検討課題は、(1)医療事故調査制度等に関するアンケート調査から見えてくることへの対応、(2)医療と刑事司法の関わり方、(3)無過失補償制度のあり方、などさまざまな視点から患者安全を推進するために周辺環境整備を含めた議論がなされています。今年度も各関連団体とも密に連携しながら、新たな課題と問題点の抽出などにも取り組んで行きます。
このような取り組みを通じて、重要事項について委員会はもとより各関連団体とも協議し、相互の理解を深めるとともに活発な議論を継続することで患者安全の実現と、わが国における医療の改善向上に資するために活動したいと考えております。関係各位には多大のご指導を賜りますようお願い申し上げます。
大学病院の医療に関する委員会 委員長

新型コロナウイルス感染症のパンデミックが収束し、大学病院の業務も本来の高度医療、高次救急、先進医療を中心とした診療と、医療人育成業務へと戻ってまいりましたが、大学病院をとりまく大きな社会の変化への対応を行わねばなりません。一つはすでに4月から開始された「医師の働き方改革」への対応です。客観的な勤怠管理が必須となり、時間外労働時間の規制や、連続勤務時間の上限設定や、代替休息のルール化等々、各大学病院で対応し実施されているものと思います。システムやルールを整備しても、いざ、行ってみると、想定していない様々な問題点が出てくるのは当然のことですから、試行錯誤がしばらくは継続するものと思います。あらかじめわかっていたことですが、本邦では人口減と過疎化が進む地域医療のニーズに対し、大学病院は診療応援を通じて適切な医療サービスの重要な担い手となっており、地方大学病院で顕著です。新潟大学病院では、常勤の医師約400名が、地域に存在する医療機関で臨時職の医師として年間24,800回の診療応援を行い、地域医療を守っております。この診療応援が行えなくなることは、地域の医療提供体制が崩れることを意味し、その社会的影響は甚大なものになることは想像に難くありません。都市部の大学病院においても、県境を越えた診療応援は常態化しており、これら機能の維持と働き方改革の両立は簡単なことではないと思います。さらに、全国の多くの2次医療圏で医療ニーズはすでにピークアウトしており、現在の医療レベルを維持しつつ(またはレベルアップを図りつつ)リストラクチャリングやダウンサイジングを行う必要性があり、そういう場面でも大学病院の果たす役割は大きいものと思われます。
しかし、大学病院の医療機関としての運営実態に目を転じますと、これらの役割を果たすための、十分な条件や体制が整備されているとは言い難いのが現状です。本委員会は、診療報酬の根幹をなす、DPC(包括評価支払制度)に関するワーキンググループ(以下WG)と経営実態・労働環境WGからなり、「大学病院の医療」に関する諸課題を明らかにし、これに対する対応策について考え、厚生労働省とも情報交換、意見交換をしながら、その社会的使命を果たせるように、大学病院全般にわたる業務改善と機能の充実を図ってまいります。皆様のご指導、ご鞭撻のほど、よろしくお願いいたします。
DPC(包括評価支払制度)に関するワーキンググループ 座長

大学病院は、研究、教育の場であるとともに、臨床においても最後の砦であることが、新型コロナウイルス感染症対応を通して、認知されたところかと思います。その大学病院が病院機能を十分に発揮し、社会的使命を果たすためには、財政基盤がしっかりしたものであることが必要です。いうまでもなく、大学病院の財政収支において、収入の最も大きい部分を占めるのが診療報酬であり、その根幹をなすのがDPC(包括評価支払制度)となります。本ワーキンググループではDPCと、大学病院の診療報酬全般の諸課題を抽出し、要望という形で、厚生労働省へ上申してまいります。
本年6月から改訂された診療報酬、DPCの大学病院の経営への影響、結果が出ているのかを取りまとめ、今年4月から施行されている医師の働き方改革への対応の影響も検討しながら、委員の皆様と議論を進め、上申を策定していきたいと思います。また、策定にあたっては、厚生労働省とも密接に情報、意見交換を行い、議論を進め、次回の診療報酬改定に反映させられるように丁寧に対応してまいりたいと思います。
皆様のご指導、ご鞭撻のほど、よろしくお願いいたします。
経営実態・労働環境ワーキンググループ 座長

この度、全国医学部長病院長会議(AJMC)の経営実態・労働環境ワーキンググループの座長を拝命いたしました富山大学の林です。前任の相良先生がまとめて来られた仕事を発展させ、継続して参る所存ですので宜しくお願い致します。
大学病院は、特定機能病院としてすべての診療機能を有し、医療安全等に経費も要する上、コロナ関連補助金がなくなり、光熱水費が著しく上昇し、物価も高騰し、さらに医師の働き方改革に伴う人件費増加も加わり、かつてないほど厳しい経営状況となっています。
このような状況においても、我々は前に進んでいく必要があり、そのために「大学病院に勤務する医師の待遇改善の取組」「医師の労働時間短縮計画に向けた取組」「研究および教育のエフォート増加に対する取組」「産業保健の仕組みの活用状況」「タスクシェア、タスクシフトに対する取組」「地域医療の支援状況」「女性医師等への支援状況」等に関する調査を行います。これらの調査の結果から、全国の大学病院の状況を把握し、今後のあるべき姿、どう変化していかなければいけないかなど、各大学病院の参考となるようにしたいと思います。文部科学省や厚生労働省の意見も取り入れ、目的達成のために活動して参りたいと思います。会員の皆様方の多大なるご支援とご指導を賜りますようお願い申し上げます。
総務委員会 委員長

昨年から総務委員会の委員長を仰せつかっております神戸大学医学部附属病院の眞庭謙昌と申します。何卒よろしくお願い申し上げます。
私は3年前に病院長に就任しましたが、当初2年間は、新型コロナウイルス感染拡大に翻弄されました。そうした状況下において全国医学部長病院長会議からの情報提供はとても心強いものでしたが、当時は対面での情報交換は叶わず、そうした機会の重要性をつくづく実感することにもなったように思います。幸い、本感染症も5類に変更になり、この1年は対面の場で皆様から貴重な情報をいただき、改めてありがたく感じている次第です。この1~2年は物価高、人件費のアップ、それに医師の働き方改革が絡む形で、大学病院の経営も厳しさを増しており、こうした状況の中での情報共有、連携は益々重要になってきております。総務委員会におきましては、特定の委員会の枠を越える問題、課題を中心に対応、調整を担っています。まずは会長、副会長をしっかりと補佐し、皆様方と密に情報を共有させていただいたうえで、課題解決に努めてまいりますので、ご指導、ご鞭撻のほどよろしくお願い申し上げます。
臨床研究・利益相反検討委員会 委員長

臨床研究・利益相反検討委員会では、臨床研究や個人・組織の利益相反の管理のあり方を示すとともに、臨床研究について文科省、厚労省、製薬協、日本医学会などの関連団体と意見交換を積極的に進め、臨床研究の円滑推進を目標に事業を進めています。
本年度の事業として、①昨年度に引き続き、企業が関与する講演会等において企業側がスライドをチェックする件の検討と改善策の提案、②医学研究の発展のために必要な奨学寄附金に関する検討、③AJMCが示す利益相反および臨床研究に関する各種ガイドラインや指針の改訂、④会員施設において円滑に臨床研究が推進されるよう臨床研究法の問題点の抽出や組織における利益相反に関する現状把握のため、アンケート調査の実施、などを予定しています。
アカデミア研究者の立場に立った環境整備と企業との適切な関係を提案したいと思います。ご協力とご支援をお願いします。
DEI(ダイバーシティ・エクイティ&インクルージョン)推進委員会 委員長
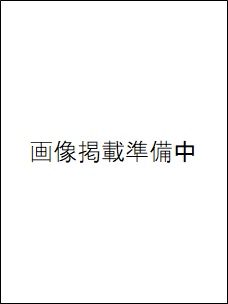
(掲載準備中)
広報委員会 委員長

広報委員会の役割は、全国医学部長病院長会議における活動を、広く社会にわかりやすく広報していくことにあります。我が国を含む世界中の医学・医療を取り巻く環境は激変しており、本会議の活動は、医療界のみならず、行政や産業界をはじめ、国民の皆さまに対して非常に大きな責任を担っています。本会議の活動の内容や成果を、ホームページ、広報誌、記者会見などを通じて、できるだけわかりやすい言葉で、正確かつ迅速に、広く広報していくことは大変重要な責務であると考えています。ホームページにおける情報発信を、よりわかりやすく、見やすくするために、つねに改善を加えて行きたいと思います。さらに、本会議の方向性やメッセージ、声明などについても、皆さまのご理解が得られるよう、皆さまに見えるかたちで活動を行っていきたいと思います。是非、よろしくお願い申し上げます。
被災地医療支援委員会 委員長

令和6年6月より松村到先生の後任として委員長を拝命しました張替でございます。よろしくお願い申し上げます。
本委員会は、東日本大震災による被災地への医療支援を取り扱う委員会として創設されました。本委員会の主な目的は、東日本大震災のような大災害が起こった際に被災地からの医療支援要請に応じて、AJMCや日本医師会など23組織(42団体)から構成される被災者健康支援連絡協議会と連携し、医師の派遣など被災地に必要な医療を提供することです。
近年、国内・周辺地域での震災が多発しており、今年の初頭には能登半島地震により大きな被害が出たことも記憶に新しいところです。また、気候変動によりこれまでとはレベルが違う集中豪雨も多く経験されており、局所的な災害の頻度も高まっています。これら災害に対し、迅速かつ適切な対応がとれるよう、委員会として何をすべきかを平時から意識し、委員の方々と準備しておきたいと考えております。
災害の発生時には、AJMCの会員の皆様には多くのご負担をお願いすることとなりますが、国民の命・生活を守るためにご協力の程よろしくお願い申し上げます。
医師の働き方改革検討委員会 委員長

2024年4月からついに医師の働き方改革が開始されました。今後、2035年度末を目標にB水準・連携B水準を終了させるべく、勤務時間短縮計画を着実に実施していく必要があります。本務並びに兼業先における時間外労働の正確な把握と適切な管理が進んでいますが改善の余地があります。また、連続勤務やインターバルの制限があるため、ある程度余裕のある医師の確保が必要不可欠ですし、多職種連携によるタスクシフト・シェア、主治医制からチーム制への診療体制の移行、患者・家族への説明の勤務時間内の実施が必要です。医師自身の健康管理とワークライフバランスの観点からは優れた制度ですが、一方で、昨今問題となっている研究力の低下、地域医療への影響、勤務医の収入減など、解決すべき多くの課題が含まれています。また、十分なコミュニケーションの時間を確保し、患者の気持ちに寄り添う診療姿勢の在り方が損なわれることのないよう、注意すべきと考えます。
本委員会では、医師の働き方改革に向けた諸課題の解決と、効率的で良好な医療の提供が実現できる方策を検討したいと思います。
医学部・医科大学の白書調査委員会 委員長

全国医学部長病院長会議(AJMC)では1993年から2年ごとに「わが国の大学医学部・医科大学白書」を調査・発行しています。本白書は、「大学の評価体制・組織運営」、「医学教育」、「臨床研修」、「大学院と研究」、「大学附属病院」、「社会および地域への貢献」、「国際交流・貢献」の分野に分けて、質問を作成し、調査した内容を整理、まとめています。その質問項目は膨大かつ多岐に亘ります。
本白書に求められるものは、調査内容の継続性から医学部・医科大学の時代の変遷をつかみ取り、一方、時代に相応した調査内容の検討から、最新の状況や取組みを把握することであると考えます。本白書には、それぞれの大学や附属病院で懸案となっている課題に関して、全国の大学の現状を把握し、他大学との比較等を通して、皆様の今後の大学運営や病院運営に役立つ内容が豊富に含まれています。さらには2020年度版からは学生へのアンケート、2022年度版からは臨床研修医へのアンケート調査結果も本白書に盛り込んでおり、学生や臨床研修医の生の声も知ることができます。
このように、本白書は重要なメッセージを発信してきましたが、2021年4月に「医学部・医科大学の白書調査委員会」として独立、立ち上げることがAJMC理事会で決定されました。この重要な本委員会委員長を2022年春から仰せつかり、身の引き締まる思いであります。本白書の制作にあたっては各大学には膨大なアンケート調査という大きなご負担をお願いしています。それだからこそ、各大学の皆様が参考にし、大いに活用していただける調査内容と白書にしたいと考えております。関係各位からのご指導とご協力をお願いいたします。
カリキュラム調査委員会 委員長

前年度に引き続き、カリキュラム調査委員会委員長を拝命いたしました聖マリアンナ医科大学の伊野美幸です。何卒よろしくお願い申し上げます。
本委員会は全国医学部長病院長会議の調査研究事業として、全国医学部のカリキュラムの現状調査を担当しております。その歴史は古く、1975年より「医学教育カリキュラムの現状」として隔年で報告書を発行しております。
我が国の医学教育は時代により変遷を重ね、現在では国際基準に準拠したカリキュラムの構築、卒前卒後教育のシームレス化、共用試験の公的化が進んでおります。また、新型コロナウイルス感染症パンデミックを契機にICTを駆使した教育が飛躍的に普及し、加えて現時点では限定的ですが、AIの導入も始まり、医療や医学教育の変革が続くことが予想されます。
今後も引き続き、医学部の医学教育改革の動向を把握し、我が国の医学教育カリキュラムについての公的調査の役割を遂行する所存です。
アンケート調査につきましては、毎回、各大学医学部関係者の皆様にご回答をいただきまして、心より御礼申し上げます。 今後とも何卒よろしくお願い申し上げます。
医学教育委員会 委員長

昨年に引き続き、本委員会を担当させていただくこととなりました。本委員会は、AJMCの医学教育に関わる部門、すなわち4つのワーキンググループ(医師養成のグランドデザイン検証WG、国家試験改善検討WG、卒後臨床研修検討WG、専門医に関するWG)、大学医学部入学試験制度小委員会、共用試験検討委員会、そしてカリキュラム調査委員会が連携し、入試から学部教育、卒後臨床研修、専門医教育まで、医学教育全般に関することを検討する委員会です。公的化された共用試験が実施され、働き方改革が施行される中で、お忙しい教員の先生方に過剰な負担をかけることなく高い教育の質を維持することが重要と考えております。医学教育委員会は、これらの課題に関して、状況分析と議論を深め、各大学が実施する医学教育の充実に貢献したいと考えておりますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。
大学医学部入学試験制度検討小委員会 委員長

2025年度より当小委員会の委員長を拝命いたしました、秋田恵一です。当小委員会は、医学部入試を公正に行うための規範を整備し、実施状況をモニターすることを目的として、2018年に設置され、これまで入試の公正さの検証を進めてまいりました。
医学部入試は、学力のみを評価するのではなく、思考力や協調性も含む人間力を含めた多面的な資質を評価することが求められます。その中で、とくに公正さの確保が重要となります。また、一般選抜に加えて、学校推薦型入試、帰国生や外国人などのための特別入試、さらには地域特別枠入試など、非常に多くの種類の入試も行われています。こうした全国医学部の様々な入試の方法や、それによる効果などについて、これまでの委員会ではアンケート調査を通じてまとめ、入学試験の実態と課題を明らかにしてこられました。
当小委員会では、これまでの検証で明らかになった課題に取り組みつつ、新たなアンケート調査の実施も検討し、より実態に即した改善のための検証を進めてまいります。皆様のご指導とご協力をお願い申し上げます。
国家試験改善検討ワーキンググループ 座長

医師国家試験は、卒前教育・卒後臨床研修などの一連の医師養成過程の中に位置付けられており、医学部のカリキュラムに大きな影響を与えています。医道審議会医師分科会の方針に従い、CBT、OSCEは共用試験として公的化が進みました。本来は、この変化に対応して医師国家試験も改革が進むことになっています。しかし、実際には国家試験は前例踏襲の旧態依然とした体制であり、大きな変化がありません。医学生が各段階で適正な評価を受けることはよいことですが、現状はいわゆる「評価疲れ」の状態となり医学生の大きな負担となっています。
モデル・コア・カリキュラムが整備され、JACMEの認証により、各大学医学部の教育体制の標準化が進んでいます。医学知識はCBT、臨床技能・態度はPre-CC
とPost-CCのOSCEで公的な評価を受けるようになった今日、医師国家試験に求められる役割は大きく変化しているのではないでしょうか。
本WGは、毎年、学生、教員を対象として「医師国家試験に関するアンケート調査」を独自に行い、この結果に基づいて厚生労働省など関係機関に要望書を提出し、医師国家試験の改善に向けて活動してきました。今後も、アンケート結果を基に、医師国家試験の現状と今後のあり方について検証を重ね、実質的な医師国家試験の改善に結びつくように要望をまとめるだけでなく、関係省庁と現実的なディスカッションを行っていきたいと考えています。みなさまにもぜひ建設的な意見をお寄せいただきますよう、よろしくお願い申し上げます。
卒後臨床研修検討ワーキンググループ 座長

卒後臨床研修制度が導入されて約20年間が経過し、医師の地域偏在と診療科偏在、医師としてのプロフェッショナリズムの低下、大学病院の医師派遣機能の減退などの課題が指摘されています。医師の地域偏在の解消に向けた都道府県別のシーリングの設定に加え、2022年度の改訂では、医学教育モデル・コアカリュキラムとの整合性の推進、研修の到達目標の策定、大都市圏の募集定員の圧縮、必修分野に一般外来研修の追加、などが適用されましたが、その実効性には検証が必要です。大学病院の研修医数は減少しており、2024年度のマッチング率は35.3%となっています。大学病院の研修医を充足する方策を検討する必要があります。また2026年度以降に開始される研修制度の見直しについては、研修病院の指定基準、小児科・産科プログラムの運用、研修病院の第三者評価、広域連携型プログラム、などに関する協議が進められています。
卒後臨床研修検討ワーキンググループでは、諸課題の解決と今後の在り方について検討を進めてまいります。引き続きご協力とご支援を賜りますようお願い申し上げます。
専門医に関するワーキンググループ 座長

日本専門医機構が平成26年5月に発足したことに伴い創設されたWGです。
全国医学部長病院長会議(AJMC)としては、大学病院が19基本領域ならびにサブスペシャルティ(以下サブスペ)領域における研修基幹病院の多くを担っていることもあり、日本専門医機構と密接に関わりながら、AJMC内の意見を集約し、内外に発信・提言していくのが使命と考えております。
現在WGが取り扱っている内容としては、地域枠医師の不同意離脱者に対する機構の対応、サブスペシャルティ領域の機構認定、医師偏在是正のために行われているシーリング制度やマッチング制度の適応、臨床研究コースの活性化を含む研究力強化などについて議論しており、令和7年度の活動についても、上記の内容についてWGで議論し、必要に応じて発信・提言を行っていきたいと考えております。
共用試験検討委員会 委員長

(掲載準備中)
研究・医学部大学院のあり方検討委員会 委員長

いま日本の医学研究は大きな岐路に立っていると言えます。かつては米欧に比肩し、多くの成果をあげて世界の医学・医療を牽引してきた日本の医学研究は、いまや米欧のみならず中国にも遥かに遅れを取り、医学に限らず研究全体としてはイランにさえも抜かれ世界13位となっています。依然としてGDP世界第4位の経済大国である日本の科学が、どうしてこのような状況となっているのか様々な複合要素が考えられますが、医学研究に関していえば、医学教育における標準化・参加型臨床実習の導入による臨床偏重や初期研修医制度・新専門医制度による若手医師の研究離れ、先進的医療を担う基幹病院での経営状況の逼迫などが挙げられるでしょう。しかしながら、日本の医学部は単なる医師養成学校になってはいけません。不治の病を研究し、新たな治療を解明し、人類の未来に貢献する責務が医学部にはあります。本委員会では、日本の医学研究を活性化させるために、医学研究及び医学部大学院のあり方を議論して提言していきたいと考えております。
動物実験検討委員会 委員長

この度、全国医学部長会議動物実験検討委員会の委員を拝命いたしました筑波大学の武井陽介と申します。
本委員会は、各大学の適切な自主管理により動物実験が円滑に実施され、人類の健康と福祉の増進につながる科学技術の発展に寄与する体制構築を目的として活動してまいりました。
今後、委員の皆様とともに、我が国の動物実験のあり方について建設的な議論を深め、科学技術の発展と動物愛護の調和を図りながら、適切な動物実験環境の構築に努めてまいりますので、ご指導ご協力のほどよろしくお願いいたします。
地域の医療及び医師養成の在り方に関する委員会 委員長
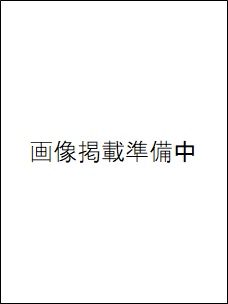
(掲載準備中)
患者安全推進委員会 委員長

この度、「患者安全推進委員会」の委員長を拝命させて頂きました日本大学医学部の木下浩作です。どうぞよろしくお願い申し上げます。
本委員会は、「医療に対する安全・安心をより向上させる」という意味を込め「患者安全推進委員会」と改称され、これまでも活発な議論が行われてきました。最近の主な検討課題は、(1)医療事故調査制度等に関するアンケート調査から見えてくることへの対応、(2)医療と刑事司法の関わり方、(3)無過失補償制度のあり方、などさまざまな視点から患者安全を推進するために周辺環境整備を含めた議論がなされています。今年度も各関連団体とも密に連携しながら、新たな課題と問題点の抽出などにも取り組んで行きます。
このような取り組みを通じて、重要事項について委員会はもとより各関連団体とも協議し、相互の理解を深めるとともに活発な議論を継続することで患者安全の実現と、わが国における医療の改善向上に資するために活動したいと考えております。関係各位には多大のご指導を賜りますようお願い申し上げます。
大学病院の医療に関する委員会 委員長

新型コロナウイルス感染症の流行を経て、大学病院は高度医療や高次救急、先進的な治療の提供、そして医療人育成という本来の使命に立ち返りつつあります。しかしながら、医療を取り巻く環境は大きく変化しており、私たちはその課題に真摯に向き合わねばなりません。
その一つが「医師の働き方改革」です。勤怠管理や労働時間の上限設定など新たな取り組みが進んでおりますが、現場では地域医療を守るための診療応援なども不可欠であり、両立には多くの困難があります。さらに、人口減少や医療需要の変化に伴い、地域ごとに体制の最適化を進める必要性が増しています。加えて、医療機関の経営状況は一段と厳しさを増しています。診療報酬の制約、人材確保の難しさ、設備更新に伴う負担など、大学病院も例外ではありません。
その中で持続可能かつ質の高い医療を提供し続けるためには、経営基盤の強化と制度的な支援が不可欠です。本委員会では、診療報酬制度や経営・労働環境に関する検討を重ね、厚生労働省や関係機関と協力しながら、大学病院の使命を果たせる体制づくりを進めてまいります。皆さまのご理解とご支援を心よりお願い申し上げます。
DPC(包括評価支払制度)に関するワーキンググループ 座長

「DPC(包括評価支払制度)に関するワーキンググループ」は、大学病院の経営基盤を支える診療報酬制度、特にDPC制度に関する課題を検討し、改善提言を行う組織です。大学病院は教育・研究の中核であるとともに、臨床においても地域医療の最後の砦として重要な役割を果たしています。しかし現在、医療費抑制や人件費の増大、働き方改革への対応などにより、多くの大学病院が厳しい経営環境に置かれています。こうした状況の中で、DPCデータを活用した精緻な経営分析と、それに基づく経営改革の推進がこれまで以上に重要となっています。
本ワーキンググループでは、診療報酬改定やDPC制度の変更が大学病院の経営に及ぼす影響を検証し、医師の働き方改革との関連も踏まえながら、現場の課題を整理・抽出します。得られた結果は厚生労働省に上申し、次回の診療報酬改定に反映させることを目指しています。
今後も、大学病院が社会的使命を果たし続けるため、制度的・財政的支援のあり方を検討し、持続可能な医療提供体制の確立に貢献していきたいと思いますので、ご支援の程よろしくお願い申し上げます。
経営実態・労働環境ワーキンググループ 座長

この度、全国医学部長病院長会議(AJMC)の経営実態・労働環境ワーキンググループの座長を拝命いたしました富山大学の林です。前任の相良先生がまとめて来られた仕事を発展させ、継続して参る所存ですので宜しくお願い致します。
大学病院は、特定機能病院としてすべての診療機能を有し、医療安全等に経費も要する上、コロナ関連補助金がなくなり、光熱水費が著しく上昇し、物価も高騰し、さらに医師の働き方改革に伴う人件費増加も加わり、かつてないほど厳しい経営状況となっています。
このような状況においても、我々は前に進んでいく必要があり、そのために「大学病院に勤務する医師の待遇改善の取組」「医師の労働時間短縮計画に向けた取組」「研究および教育のエフォート増加に対する取組」「産業保健の仕組みの活用状況」「タスクシェア、タスクシフトに対する取組」「地域医療の支援状況」「女性医師等への支援状況」等に関する調査を行います。これらの調査の結果から、全国の大学病院の状況を把握し、今後のあるべき姿、どう変化していかなければいけないかなど、各大学病院の参考となるようにしたいと思います。文部科学省や厚生労働省の意見も取り入れ、目的達成のために活動して参りたいと思います。会員の皆様方の多大なるご支援とご指導を賜りますようお願い申し上げます。
総務委員会 委員長
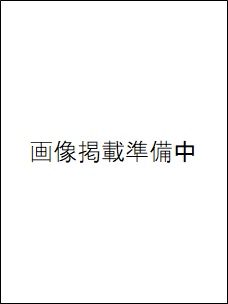
(掲載準備中)
臨床研究・利益相反検討委員会 委員長

臨床研究・利益相反検討委員会では、臨床研究や個人・組織の利益相反の管理のあり方を示すとともに、臨床研究について文科省、厚労省、製薬協、日本医学会などの関連団体と意見交換を積極的に進め、臨床研究の円滑推進を目標に事業を進めています。
本年度の事業として、①昨年度に引き続き、企業が関与する講演会等において企業側がスライドをチェックする件の検討と改善策の提案、②医学研究の発展のために必要な奨学寄附金に関する検討、③AJMCが示す利益相反および臨床研究に関する各種ガイドラインや指針の改訂、④会員施設において円滑に臨床研究が推進されるよう臨床研究法の問題点の抽出や組織における利益相反に関する現状把握のため、アンケート調査の実施、などを予定しています。
アカデミア研究者の立場に立った環境整備と企業との適切な関係を提案したいと思います。ご協力とご支援をお願いします。
DEI(ダイバーシティ・エクイティ&インクルージョン)推進委員会 委員長

本委員会は、会員大学の医師が属性によらず、あらゆる分野で輝いて活躍できる環境整備を目指しています。わが国における医師の労働時間、診療科選択、キャリア形成などの就労状況は、女性医師のキャリア形成の課題のみならず、働き方改革や介護負担などにより、劇的に変化を続けています。本委員会では令和2年度から隔年で会員大学ならびに医師に対する意識調査を行い、誰もが輝いて活躍するために、以下の4つを提言してきました。
1.性別役割分担意識の是正と男女共同参画体制の推進
2.家事、育児、介護などの家庭生活を支援する社会基盤の充実
3.長時間労働の是正と業務内容の効率化
4.大学・大学病院に勤務する医師の経済的基盤の充実
令和6-7年度は労働時間、職場環境、生活基盤などの働きやすい環境整備が前進したか、これまでの意識調査と比較するとともに、介護休暇制度や男性の育児休暇取得体制など、更なる改善の方向などについての調査・分析することで、働きがいのある環境整備を推進するための提言を行う予定です。
今後も、これまでの当委員会活動が積み重ねてきた成果を更に発展させてまいりたいと思いますので、引き続きご指導とご支援をお願い致します。
広報委員会 委員長
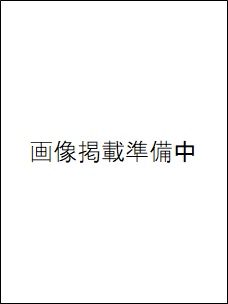
(掲載準備中)
被災地医療支援委員会 委員長

令和6年6月より松村到先生の後任として委員長を拝命しました張替でございます。よろしくお願い申し上げます。
本委員会は、東日本大震災による被災地への医療支援を取り扱う委員会として創設されました。本委員会の主な目的は、東日本大震災のような大災害が起こった際に被災地からの医療支援要請に応じて、AJMCや日本医師会など23組織(42団体)から構成される被災者健康支援連絡協議会と連携し、医師の派遣など被災地に必要な医療を提供することです。
近年、国内・周辺地域での震災が多発しており、今年の初頭には能登半島地震により大きな被害が出たことも記憶に新しいところです。また、気候変動によりこれまでとはレベルが違う集中豪雨も多く経験されており、局所的な災害の頻度も高まっています。これら災害に対し、迅速かつ適切な対応がとれるよう、委員会として何をすべきかを平時から意識し、委員の方々と準備しておきたいと考えております。
災害の発生時には、AJMCの会員の皆様には多くのご負担をお願いすることとなりますが、国民の命・生活を守るためにご協力の程よろしくお願い申し上げます。
医師の働き方改革検討委員会 委員長

2024年4月からついに医師の働き方改革が開始されました。今後、2035年度末を目標にB水準・連携B水準を終了させるべく、勤務時間短縮計画を着実に実施していく必要があります。本務並びに兼業先における時間外労働の正確な把握と適切な管理が進んでいますが改善の余地があります。また、連続勤務やインターバルの制限があるため、ある程度余裕のある医師の確保が必要不可欠ですし、多職種連携によるタスクシフト・シェア、主治医制からチーム制への診療体制の移行、患者・家族への説明の勤務時間内の実施が必要です。医師自身の健康管理とワークライフバランスの観点からは優れた制度ですが、一方で、昨今問題となっている研究力の低下、地域医療への影響、勤務医の収入減など、解決すべき多くの課題が含まれています。また、十分なコミュニケーションの時間を確保し、患者の気持ちに寄り添う診療姿勢の在り方が損なわれることのないよう、注意すべきと考えます。
本委員会では、医師の働き方改革に向けた諸課題の解決と、効率的で良好な医療の提供が実現できる方策を検討したいと思います。
医学部・医科大学の白書調査委員会 委員長

全国医学部長病院長会議(AJMC)では1993年から2年ごとに「わが国の大学医学部・医科大学白書」を調査・発行しています。本白書は、「大学の評価体制・組織運営」、「医学教育」、「臨床研修」、「大学院と研究」、「大学附属病院」、「社会および地域への貢献」、「国際交流・貢献」の分野に分けて、質問を作成し、調査した内容を整理、まとめています。その質問項目は膨大かつ多岐に亘ります。
本白書に求められるものは、調査内容の継続性から医学部・医科大学の時代の変遷をつかみ取り、一方、時代に相応した調査内容の検討から、最新の状況や取組みを把握することであると考えます。本白書には、それぞれの大学や附属病院で懸案となっている課題に関して、全国の大学の現状を把握し、他大学との比較等を通して、皆様の今後の大学運営や病院運営に役立つ内容が豊富に含まれています。さらには2020年度版からは学生へのアンケート、2022年度版からは臨床研修医へのアンケート調査結果も本白書に盛り込んでおり、学生や臨床研修医の生の声も知ることができます。
このように、本白書は重要なメッセージを発信してきましたが、2021年4月に「医学部・医科大学の白書調査委員会」として独立、立ち上げることがAJMC理事会で決定されました。この重要な本委員会委員長を2022年春から仰せつかり、身の引き締まる思いであります。本白書の制作にあたっては各大学には膨大なアンケート調査という大きなご負担をお願いしています。それだからこそ、各大学の皆様が参考にし、大いに活用していただける調査内容と白書にしたいと考えております。関係各位からのご指導とご協力をお願いいたします。
カリキュラム調査委員会 委員長

前年度に引き続き、カリキュラム調査委員会委員長を拝命いたしました聖マリアンナ医科大学の伊野美幸です。何卒よろしくお願い申し上げます。
本委員会は全国医学部長病院長会議の調査研究事業として、全国医学部のカリキュラムの現状調査を担当しております。その歴史は古く、1975年より「医学教育カリキュラムの現状」として隔年で報告書を発行しております。
我が国の医学教育は時代により変遷を重ね、現在では国際基準に準拠したカリキュラムの構築、卒前卒後教育のシームレス化、共用試験の公的化が進んでおります。また、新型コロナウイルス感染症パンデミックを契機にICTを駆使した教育が飛躍的に普及し、加えて現時点では限定的ですが、AIの導入も始まり、医療や医学教育の変革が続くことが予想されます。
今後も引き続き、医学部の医学教育改革の動向を把握し、我が国の医学教育カリキュラムについての公的調査の役割を遂行する所存です。
アンケート調査につきましては、毎回、各大学医学部関係者の皆様にご回答をいただきまして、心より御礼申し上げます。 今後とも何卒よろしくお願い申し上げます。
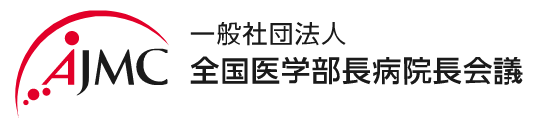
昨年に引き続き、本委員会を担当させていただくこととなりました。本委員会は、AJMCの医学教育に関わる部門、すなわち4つのワーキンググループ(医師養成のグランドデザイン検証WG、国家試験改善検討WG、卒後臨床研修検討WG、専門医に関するWG)、大学医学部入学試験制度小委員会、共用試験検討委員会、そしてカリキュラム調査委員会が連携し、入試から学部教育、卒後臨床研修、専門医教育まで、医学教育全般に関することを検討する委員会です。公的化された共用試験が実施され、働き方改革が施行される中で、お忙しい教員の先生方に過剰な負担をかけることなく高い教育の質を維持することが重要と考えております。医学教育委員会は、これらの課題に関して、状況分析と議論を深め、各大学が実施する医学教育の充実に貢献したいと考えておりますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。